【保存版】知って安心。香典返しの基本ガイド

お葬式や法要のあと、香典をいただいた方へお礼としてお渡しする「香典返し」。それは単なる品物のやり取りではなく、故人を偲んでくださったお気持ちに、遺族として感謝をお伝えする大切な習慣です。
香典返しは地域や宗派によってしきたりや時期が異なり、迷ってしまう方も多いもの。この記事では、一般的とされる香典返しの基本と、誰もがわからなくなる、迷いがちなケースにおける対応について、まとめました。
この記事の執筆者
 Hanaimo(花以想)店主
Hanaimo(花以想)店主
目次
香典返しとは
香典返しとは、葬儀や法要でいただいた香典や供物に対して感謝の気持ちを込めてお贈りする品物のことです。もともとは、仏前に香を供える「香奠(こうでん)」から生まれた言葉。今では仏式だけでなく、神式やキリスト教式でも形を変えて受け継がれています。

香典返しの時期
一般的には「四十九日の忌明け以降」にお届けします。四十九日の忌明け法要までは忌中ですから、その間は礼状や香典返しも控えます。これは、四十九日が故人が成仏し一区切りを迎えるとされる節目だからです。
香典返しは「おかげさまで四十九日(満中陰)の法要を相営み忌明けしました」というご挨拶ともいえます。
なお地域によっては、三十五日や百か日を目安にすることもあります。わからないときには身近な親族やお寺に相談しながら決めると安心です。

香典の「当日返し」「忌明け返し」とは?
当日返しは、通夜、葬儀の当日に、香典をいただいた方にお礼をこめて、その場で返礼品をお渡しする方法で、「その場返し」ともいいます。これは遠方から来られた方への配慮になるとともに、後日改めてのお礼する必要がないので、段階的な予定を立てずに済むのが利点です。
忌明け返しは、四十九日を終えてからまとめてお贈りする方法。香典帳を整理して金額に応じた品を選べるため、添える挨拶文に想いをこめるなど、より丁寧なお礼ができます。
香典返しの方法と特徴まとめ
| 種類 | タイミング | 特徴・メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 当日返し | 葬儀当日 | ・その場でお渡しできる ・遠方からの参列者に配慮できる | ・忌明けを待たないため地域によっては好まれない場合あり |
| 忌明け返し | 四十九日など忌明け後 | ・香典帳を整理して金額に応じた品を選べる ・より丁寧なお礼ができる | ・発送準備や管理に時間と手間がかかる |
香典返しの金額相場
香典返しの目安は、一般的に「半返し」が基本とされ、香典額の三分の一から半分程度の品をお返しします。たとえば1万円の香典には5千円程度が目安。なお実際には、香典には「不時の出費の相互扶助」という意味もあるので、亡くなられた方の立場や関係をもとに判断するのがよいでしょう。
香典返しの掛け紙(懸け紙)について
掛け紙には「志」「満中陰志」「偲び草」など、宗派や地域に合わせた表書きを用います。
水引は、仏式では黒白や双銀、神式は双白、キリスト教では銀一色など、宗教によって選び方が異なります。
香典返しの掛け紙と水引の種類(宗教別)
| 宗教・宗派 | 表書きの例 | 水引の色・形 |
|---|---|---|
| 仏式 | 志、満中陰志 | 黒白、双銀、黄白(関西) |
| 神式 | 偲び草 | 双白 |
| キリスト教 | 志、偲び草(宗派により異なる) | 銀一色 |
高額の香典をいただいた場合はどうする?
たとえば親戚やお世話になった方から、著しく高額な香典をいただくこともあるかもしれません。そんな場合には、一般的な「半返し」以上のお品をお届けする場合もあります。具体的には、カタログギフトや上質な食品など、相手に負担をかけない品を選ぶのが無難です。
なお、親族で高額な香典を包まれた方は、相互扶助の目的が強いと考えられます。その場合は必ずしも額にとらわれない選択をしてもよいでしょう。
香典返しには供花の分も含めていい?
生花や花輪も「お供え」として香典返しの対象に含める場合があります。ただし、地域やご家庭の考え方によるため、判断に迷うときは事前に相談するのがおすすめです。
弔電のみ、生花・花輪のみ頂いた場合どうする?
弔電のみの方には返礼品は不要ですが、お礼状やお電話で感謝をお伝えするのが望ましいです。
生花や花輪のみの場合は、香典と同様に半返しを行う地域もあり、その場合はお茶やお菓子など日持ちする品が選ばれます。
「三月またぎ」ってなんのこと?
忌明け返しの時期が月をまたぐことを「三月またぎ」または「三月掛け」と呼びます。これはお祝い事や弔事のお返しなどを三か月にわたって行うのはよくないという、ある種の迷信です。縁起を気にして避ける地域、それを気にされる親戚などが要る場合には、お寺の方や僧侶に相談することをおすすめします。
喪中はがき後に香典をいただいた場合は?
喪中はがきをお送りした後に香典をいただくこともあります。その場合は一週間から十日後に先方に着くように、「志」の掛け紙で挨拶状とお返しを贈ります。挨拶状は「ご厚志を賜り、誠にありがとうございました」と簡潔に述べれば十分です。
お盆やお彼岸に香典返しを送るのは避けるべき?
お盆やお彼岸に香典返しが届くのは、弔事と重なって好まれない場合があります。宅配の混雑時期でもあるため、到着日は少しずらす配慮が安心です。
香典返しをいただいた場合のお礼は必要?
香典返しを受け取った側は、基本的にお礼の必要はありません。ただし、親しい関係であれば「無事に忌明けを迎えられたことを安堵しています」と一言伝えると、相手の心も和らぎます。
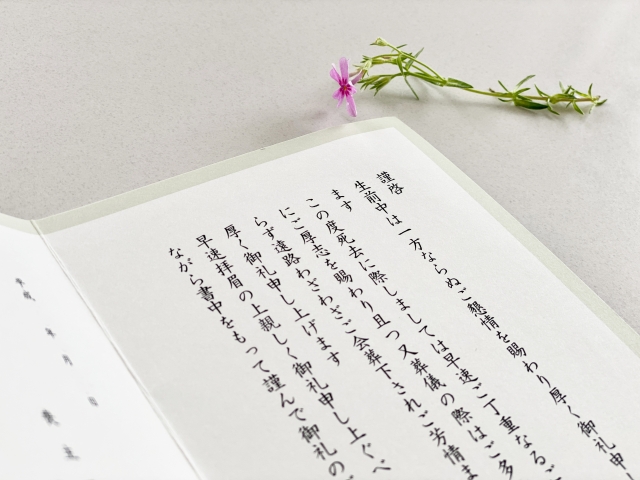
香典に添える、返礼挨拶状の書き方
香典返しは、品物だけでなく「挨拶状」で感謝をしっかりと伝えることが大切です。文章の調子や表現には一定のマナーがあり、特に弔事は慎重さが求められます。
1. 書き方のポイント
- 時候の挨拶は省略する
- 弔事の挨拶状では、季節のあいさつやお祝いごとで使うような言葉は避けます。
- 代わりに、訃報と香典へのお礼から始めるのが基本です。
- 謹んだ言葉遣いを使う
- 「お礼申し上げます」よりも「厚く御礼申し上げます」など、控えめで丁寧な表現を選びます。
- 「めでたい」や「喜び」に関する言葉は入れません。
- 亡くなった日・法要日を明記する
- 「故○○儀 ○月○日に永眠いたしました」
- 「このたび○月○日に四十九日の法要を滞りなく相済ませました」など。
- 香典返しの品を贈る旨を伝える
- 「心ばかりの品をお贈りさせていただきます」など、控えめに記します。
- 結びの言葉で感謝とお願いを添える
- 「今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます」など、遺族としてのお願いを含めて締めます。
2. 注意点
- 句読点を使わない
- 弔事文では「悲しみが途切れない」ことを避けるため、句読点は使わず改行やスペースで区切ります。
- 宗教・宗派に合わせる
- 仏式:四十九日/満中陰志
- 神式:五十日祭/偲び草
- キリスト教式:召天日/記念会など、用語を合わせます。
- 不吉な連想を避ける言葉は使わない
- 「再び」「重ねて」など、不幸が繰り返される印象のある言葉は避けます。
- 送り主名の書き方
- 喪主または遺族代表者のフルネームを記載します。家族連名の場合は代表者名を先に書き、続柄や連名を添えます。
- 印刷でも手書きでも整った形で
- 印刷文でも構いませんが、封筒やはがきに一筆手書きで添えるとより温かみが伝わります。
まとめ
香典返しは、形式にとらわれるよりも「感謝の気持ち」を伝えることが一番大切です。
地域や宗派の習わしを尊重しつつ、贈る側も受け取る側も、心が少し温かくなるようなやり取りを心がけたいものです。

この記事の監修者
フラワーギフト専門店 Hanaimo 店主 鈴木咲子
インテリア系専門学校に進学後、進路転向し花の世界に。ドイツ人マイスターフローリストに師事。2000年に渡独、アルザス地区の生花店に勤務し帰国後、2002年 フラワーギフト通販サイトHanaimo開業。趣味は読書、文学に登場する植物を見つけること。高じて『花以想の記』を執筆中。2024年 5月号『群像』(講談社)に随筆掲載。一般社団法人日本礼儀作法マナー協会 講師資格。
メッセージ・手紙 例文集
お花を贈るならHanaimoへ

